更新日:2024年5月27日

- 目次
- 公務員の種類とは? 国家公務員と地方公務員の大きく2つに大別される
- 国家公務員の仕事内容
- 地方公務員の仕事内容
- 国家公務員地方公務員に向いているのはそれぞれどういう人?
- 国家公務員の種類は、行政府・立法府・司法府の勤め先で分類できる
- 行政府の国家公務員は?
- 立法府の国家公務員は?
- 司法府の国家公務員は?
- 地方公務員は、自治体の規模・範囲で分類できる
- 市町村に勤める地方公務員は?
- 都道府県に勤める地方公務員は?
- 政令指定都市に勤める地方公務員は?
- 東京都・特別区に勤める地方公務員は?
- 公務員の種類とは?
- 行政系
- 心理系
- 福祉系
- 技術系
- 公務員の種類別試験の難易度とは?
- 受験先はどう選んだらいい?公務員試験の選び方
公務員の種類とは? 国家公務員と地方公務員の大きく2つに大別される
国家公務員の仕事内容
国家公務員には、一般にイメージされるデスクワークで書類を処理する仕事である行政事務のほか、技術職、心理・福祉職などより専門的な仕事もあります。しかし、共通しているのが「生涯特定の仕事に従事する」という点です。したがって、特定の仕事を選んでそれに従事したい人は国家公務員向きといえるでしょう。国家公務員はさらに総合職と一般職に分けられます。総合職は、一般職職員や地方公務員、民間企業などのプレーヤーがいかんなく能力を発揮できる環境を整備し、5年後10年後の日本、アジア、世界に対するビジョンをもって、「国を動かす」仕事であるのに対し、一般職は中央省庁や地方検察庁、労働局、法務局など出先機関で与えられた仕事に自分の能力を活かして貢献する仕事です。
地方公務員の仕事内容
国家公務員と同様に、地方公務員にも行政事務のほか、より専門的な仕事があります。また、消防官や警察官なども地方公務員に含まれます。地方公務員に特徴的なのは、「どの仕事であっても、様々な部署を移動することを通じて多様な業務に触れる」という点です。したがって、様々な業務に挑戦して自分の可能性を試したい人は地方公務員向きといえるでしょう。また、国家公務員と異なり、地域住民に近い立場で仕事をすることが多いことも特徴です。
国家公務員と地方公務員の仕事やなり方の違い!魅力や向いている人は?
国家公務員地方公務員に向いているのはそれぞれどういう人 ?
国家公務員の中でも総合職は国を動かす政策を企画立案する仕事なので、企画力思考力が必要となります。その場で与えられた情報を元に考え、議論できるという資質のある人が向いているといえるでしょう。これに対して一般職は国を支える仕事なので、与えられた仕事に対してきちんとルールを守り、上司や同僚、さらには部下と力を合わせて取り組める協調性のある人が向いています。国税専門官や財務専門官、労働基準監督官、裁判所職員などの専門職は、就職した後も多くの研修を積んで勉強しなければなりませんから、勉強好きな人が向いているといえるでしょう。
ただし、国政専門官は年度末に確定申告の受付などをするので、数字に強い人の方が向いています。裁判所事務官は受付や総務、財務、資料管理など仕事内容自体は市役所などの基礎自治体と共通点もあるのですが、そこを訪れる人は、たとえば事件に巻き込まれ人生の岐路に立っているので、ただ協調性があって明るければよいというものではなく、不安を抱えた来訪者に安心感を与えられるよう、的確な事務処理能力のある人が向いているといえるでしょう。
以上に対して地方公務員のうち市区町村など基礎自治体では窓口業務が欠かせませんから、どんな人とも触れ合えるコミュニケーション能力のある人が向いています。また、都道府県などの広域自治体の場合、国や他県、県内の市区町村、企業などの団体相手のBtoBの仕事ですから、団体間の利害を取り持てる調整能力のある人が向いていることになります。

- \まずはここからスタート!/
- 資料を請求する
国家公務員の種類は、行政府・立法府・司法府の勤め先で分類できる
行政府の国家公務員は?
行政府の国家公務員のトップは内閣です。内閣直属の機関として、内閣官房、内閣府、内閣法制局などがあります。他にちょっと特殊ですが、内閣直属の情報機関として、内閣情報調査局などもあります。これらの長は内閣総理大臣なので、時の総理の支持の下、大きな仕事に挑戦できます。
これらの下に一般の省庁があります。省庁の中には外務省、経済産業省、厚生労働省、国土交通省、財務省等5大官庁をはじめとした総務総、文部科学省、農林水産省、環境省などの政策系官庁と法務省、警察等、国税庁などの実施官庁等があります。これらを本省庁としてそれぞれ地方支分局、いわゆる出先機関があります。出先機関は法務省の地方検察庁や法務局や公安調査庁、厚生労働省の労働局、財務省の税関などです。
これらは内閣をトップとしその指揮監督を受けますが、行政府の国家公務員の中には例外的に内閣の指揮監督を受けない会計検査院や人事院、公正取引委員会などのいわゆる独立行政委員会などがあり、それぞれ一般の官庁には見られない特徴があります。
- 【行政府の職員】
- 国家公務員総合職
- 国家公務員一般職
- 国家公務員専門職
立法府の国家公務員は?
立法府の公務員としては、日本国憲法に置いて衆議院と参議院の二院制が採用されている結果、衆議院の職員と参議院の職員があります。衆議院の公務員としては衆議院事務局と衆議院法制局、参議院の公務員としては参議院事務局と参議院法制局があります。たとえば衆議院や参議院事務局の仕事は国会本会議をはじめとして、各種委員会や両院協議会などの運営を事務処理の側面から支援する仕事になります。また、衆議院や参議院法制局の仕事は、国会議員が提出するいわゆる議員立法の支援をする仕事です。さらに、国会の付属施設の仕事として国立国会図書館の仕事があります。国会図書館は内外の書籍類をその分野種類を問わずに保存する仕事で学術書文芸書から漫画や雑誌に至るまでの書籍、さらにはインターネットサイトの情報の保存まで行います。こうした広い意味の図書は日々出版されるわけですから、国立国会図書館の蔵書は普段に増加し続けるのであり、数年後、数十年後、数百年後の人類が今の我々の文化生活を認識するための資料を残していく重要な仕事です。
国会は国の機関の中で唯一、選挙で選ばれる国会議員によって構成される機関であり、同時に、内閣総理大臣を指名して、内閣を形作っていくということで、国民と行政の架け橋となる連結点として重要な役割を担っており、そこで働く公務員にも重い責任が課されているのです。
- 【立法府の公務員】
- 衆議院事務局職員
- 衆議院法政局職員
- 参議院事務局職員
- 参議院法政局職員
- 国立国会図書館職員 など
司法府の国家公務員は?
司法府の国家公務員には、大きく裁判所事務官と家庭裁判所調査官があります。
裁判所事務官には行政の場合と同じように総合職と一般職があります。一般職の方は地域別の採用ですが、総合職は全国転勤になります。裁判所事務官の仕事は事務局と裁判部の仕事があり。事務局の仕事は市役所などの役所の事務に似ています。裁判所事務官の仕事の特徴はなんといっても裁判部の仕事があることでしょう。裁判所事務官の一般職で採用された場合、内部試験に合格し、1年間の研修を終了すると裁判所書記官になることができます。裁判所書記官は裁判においてコートマネジメントをして裁判官を支援したり、簡単な裁判を実行したりと裁判所ならではの仕事をすることができます。ちなみに裁判所事務官総合職ですと無試験で裁判所書記官の資格を得ることができます。裁判所事務官の仕事は事務局での一般事務にとどまらず、家庭裁判所で離婚の調停に携わったり、強制執行の競売を主催したりと、通常では体験できないような様々な職務を経験することもできます。
他方、家庭裁判所調査官は一般職採用なく総合職採用のみであり、全国転勤になります。全国の家庭裁判所でたとえば、非行を犯し保護手続の対象となった少年と向き合い面談をして、心の闇に光を当て、原因を探って、裁判官に資料として提供し、効果的な処遇決定に貢献していく仕事です。家庭裁判所調査官の活躍の場は、家庭裁判所のほか鑑別所などもあります。

- 【司法府の公務員】
- 裁判所事務官
- 家庭裁判所調査官 など
地方公務員は、自治体の規模・範囲で分類できる
市町村に勤める地方公務員は?
地町村の公務員は最も小さな規模の自治体の公務員です。異動の範囲もその自治体内に限定されるため通勤の負担も比較的軽いということになります。自分の愛する故郷でさまざまな業務を経験して貢献できるというのがこうした基礎自治体の仕事です。住民からの様々な要望を受け付ける窓口業務が中心になりますから、苦情などもあり大変な所もありますが、そこの地域限定で働くことができます。窓口業務以外では、図書館の職員や議会対応で議員みなさんの支援をしたり、一人暮らしの高齢者や障害者の方を家庭訪問して見守りをしたり、広報を作って住民の皆さんに様々な情報を提供して暮らしの支援をします。
特に、最近の我が国の顕著な問題として人口減少とそれに伴う労働力不足という問題が深刻ですから、われわれの生活は在留外国人の皆さんに依存するところが大きくなっています。そこで、日本にやって来たてで、われわれの文化に慣れることができず、困惑している外国人の皆さんが、少しでも住みやすくなるよう、どこの自治体でも共生課という部署が作られるようになりました。他に、公立小中学校や消防署の運営管理も市町村の仕事です。
都道府県に勤める地方公務員は?
市町村等の基礎自治体が個々の住民相手のBtoCの仕事であるのに対して、都道府県などの広域自治体の仕事は、国や他県、県内の市町村や企業などといった団体相手の仕事であり、より大規模となります。いわば国と市町村の架け橋になるわけですが、国に対しては県内の活性化のため、高速道路のインターチェンジ、新幹線やリニアモーターカーの駅を作ってもらえるよう要請したり、他の県に対しては、自県のみでは達成できない広域課題に対して連合を呼びかけ、より効果的な取組ができるよう働きかけたり、県内の市町村に対しては、行政サービスの質を向上させるよう働きかけたり、行政事務を民間企業に委託したり、ボランティア団体に協力を仰いで、効率化を図ったり、県内の様々な自然、文化的、経済的資産を最大限効果的に活用すべく、団体への働きかけ、団体間の調整を通じて、より影響力の大きな施策を実施していく仕事をします。他に県立高校や警察の運営管理も県庁の仕事です。
政令指定都市に勤める地方公務員は?
政令市は人口50万人以上で、政令で指定された都市ですが、実際上はいわゆる「100万都市」がこれにあたります。
ひとことでいえば市役所として基礎自治体的な住民密着型の仕事ができる一方で、内部に行政区、つまり区役所を設置することができ、そういう意味では県庁に似た広域自治体的な仕事まで、一般的な市役所に比べると、より多様な仕事に取り組むことが可能となります。言い方を変えれば、基礎自治体的ステージから広域自治体的ステージまで多様な場面から、より効果的な住民サービスができるというのが政令都市の魅力といえるでしょう。たとえば、東京都特別区の区長になるには選挙で当選しなければなりませんが、政令都市内部の区の区長さんは政令都市の職員であればなることができるのです。こうした経験ができるのも政令都市職員ならではといえるでしょう。
政令都市は地域によっては、そこを含む県庁を凌ぐ力をもっている自治体もあります。たとえば、わが国最大の政令都市である横浜市では、横浜港周辺の開発計画は神奈川県よりは主として横浜市が握っているようです。さらに、横浜市は将来的に「特別自治体構想」というもの提案し、現在神奈川県が行っている事務を横浜の地域内で横浜が管轄するという構想を考えています。
東京都・特別区に勤める地方公務員は?
大都市東京という地域で公務員になろうと考えた場合、東京都庁の職員と特別区の職員が考えられます。
特別区は市町村と同じ基礎的自治体であり、異動は一つの区の中に限定されます。つまり、渋谷区の職員になれば渋谷区内だけ、新宿区に勤めれば新宿区内だけで働くことができるのです。東京都の職員のように東京都内のいろいろな分局や島に行かなくて済みます。その代わり基礎自治体なので当然仕事は窓口業務などが中心となります。他に、他の市町村などと同じ図書館勤務や広報などの勤務があります。東京都特別区の仕事の特徴として、他の自治体では福祉職員の仕事であるケースワークが通常の行政職員の仕事でもあるということです。ケースワークの対象者は一人暮らしの高齢者などであり、いわばこうした区内在住の方々の見守りをする仕事です。ケースワークには路上担当というものもあり、これは勤労意欲のある路上生活者の方の定住住所獲得から就職の支援までをワンストップで行う仕事で、これなどは確実に一人の人間を幸せにする仕事ですから大変やりがいがあります。他に近時最も外国人が増加しているのも東京の区部ですから、どこの区にも多文化共生課があります。
これに対して東京都庁の仕事は企画の仕事ひとつとっても区役所より大規模になります。たとえば、わが国の次世代エネルギーのひとつとして水素発電が国によって打ち出されていますが、それを着地させるのが都庁の仕事で、2021年の東京五輪の選手村全域に水素発電が導入されました。現在はポスト五輪にこのレガシーをどう活かし普及させるのかが都庁の職員の課題となっています。
公務員の種類とは?
公務員の職種は、担う仕事内容により分けられています。それぞれの役割や仕事内容が異なるため、ご自身が公務員として携わりたい仕事なのかなど、公務員を目指すうえで参考としてください。
行政系
行政系公務員は一般的に「行政事務」「一般事務」などと呼ばれています。国家公務員(各省庁や出先機関)や地方公務員(都道府県庁・市役所など)で働き、行政全般の幅広い業務に携わります。
例えば、役所での政策の事務処理、住民票の発行や地域の福祉関連業務、PR活動などさまざまです。特に地方公務員では3年に1度異動があるため幅広い経験を積めることから、ゼネラリストとして活躍することができるようになります。
行政系公務員になるためには「国家一般職」「地方上級」「市役所」などの試験を受験する必要があります。
心理系
心理系公務員は、心理系の専門知識やスキルを活かした業務に携わります。心理系公務員の主な仕事内容としては「国家公務員」では厚生労働省・法務省・裁判所などで活躍する場があり、「地方公務員」では児童相談所などで相談員として活躍しています。
心理系公務員になるためには「国家公務員」の場合は国家総合職、法務省専門職員、裁判所職員総合職の人間科学区分などの試験に合格する必要があります。
中には例外的に資格が必要とされる場合があるため、ご自身に資格があるか確認が必要です。
福祉系
福祉系公務員は、ケースワーカーとして児童相談所や福祉事務所などで、虐待や家庭内暴力の被害者支援、障がい者や高齢者の生活支援などを行います。国家公務員としての採用は少なく、地方公務員としての採用が多いことが特徴です。
福祉系公務員になるためには、各自治体の採用試験を受験することになりますが、一部自治体では「社会福祉士」「児童指導員」などの資格が必要になっています。多くは「社会福祉主事任用資格」を持っていれば受験可能となっていますし、資格がなくても受験できるところもあります。
技術系
技術系公務員は、「土木」「建築」「電気情報」など大学で学んだ知識を活かし、人々の生活を支える仕事に携わります。各分野の専門的な知識が求められることが特徴的です。
公務員の種類別試験の難易度とは?
同じ公務員試験でも、採用人数や科目構成、科目ごとの出題範囲や設問内容の深さ・浅さなど、ひとくくりにはできない試験の種類と難易度があります。難易度に明確な基準はありませんが下記は倍率や試験内容から独自に算出しています。
- 超難関レベル
- 国家公務員(総合職)、外務省専門職員、国会職員など
- 難関レベル
- 東京都庁・大都市圏県庁・東京特別区・政令指定都市職員(大卒)、労働基準監督官など
- 普通レベル
- 国家公務員(一般職)、地方上級(県職員)、国税専門官、裁判所事務官(一般職)、国立大学法人等職員など
- 比較的難易度が低い
- 市役所職員、消防官、警察官など
- もっと詳しく見る
公務員試験の難易度は?難しい?試験別の倍率や合格のポイントを解説!
受験先はどう選んだらいい?公務員試験の選び方
公務員試験は司法試験や公認会計士試験など他の資格試験とはことなり就職試験です。
つまり、どんな選択をするかで皆さんの人生その者が大きく変ってくるのです。仕事を決める場合、まず、考えるのが自分の個性との相性、つまり適性でしょう。また、人生の大半をこれに費やすことになるわけですから、その仕事に興味を持てるという志向性も大きな要素です。

しかし、それ以上に、自分の愛する家族との関係が最終的には重くのしかかってきます。たとえば、北海道出身のあなたが一人っ子でご兄弟がいらっしゃらなかったとして、東京都庁に努めた場合、後になってご両親の介護が必要となった場合になにが起こるでしょうか。今は、ご両親は「お前の好きなようにやっていいよ」というかもしれません。しかし、年老いて病魔に倒れ寝たきりになって要介護になった自分の親をほっておけますか?そんなとき折角軌道に乗ってきた仕事を放り出して、地元でアルバイト生活をする羽目なんかになったりしたら大変勿体無いことです。自分が社会に出てどのように貢献していきたいかという夢や夢としてしっかりと考える一方で「生活」についても考える時期になっているということです。したがって、慎重には慎重を期して、一度実家のご家族としっかりと将来を話し合う。受験先を選ぶためにもこれが一番大事なことだといえるでしょう。
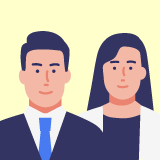
- 監修者:LEC実力派の講師陣
- LECは公務員試験の指導実績30年以上!
公務員試験を知りつくしたプロ!LEC講師陣が全国で公務員を目指す受験生のために丁寧に指導。
経験豊富な受験指導のプロが受験生の疑問や悩み・不安を解消し、最終合格・内定まで、完全サポートしていきます。
合格に導く実力の講師陣










