更新日:2024年5月27日
一般的に「公務員」と呼ばれているのは各省庁や自治体で働く行政職の方々ですが、裁判所でも「適正・迅速な裁判」の実現に向けて裁判所事務官の方々が働いています。行政職の方々がゼネラリストとして様々な業務に携わる一方、裁判所事務官は裁判所内での仕事は多岐にわたりますが、裁判を支える、という意味では、一つの目標のもとに働いている方々です。ただし、採用試験自体は行政職とそれほど大きく異なるわけではありませんので、第一志望の人はもちろん、併願先としての人気も高いです。裁判所事務官について今回は解説していきます。

裁判所事務官とは?どんな仕事内容?
裁判所事務官は採用された後には裁判部や事務局に配置され、「適正・迅速な裁判」の実現を支えています。具体的には、事務局では総務課や会計課、人事課などにおいて、事務全般に従事します。総務部の仕事は裁判の現場ではないですが、裁判所全体を支える屋台骨です。一方、裁判部では、裁判所書記官のもとで検察官や弁護人の方々などとの間の書類の授受を担当したり、開廷前の法廷の準備を行ったり、証人や裁判員裁判に参加する裁判員の方々の接遇など、各種の裁判事務に従事します。裁判所書記官は、「公証官」として裁判手続の経過を公に証明するために、法廷で行われた手続や内容は「調書」にまとめますが、そのような法廷内での書記官の仕事がスムースに進むように、チームの一員として補佐していくのが事務官の役割になります。
裁判所で働く公務員の種類
裁判所の組織は大きく裁判部と事務局に大きく分かれています。裁判部では各種の事件を裁判官が審理・裁判しますが、その裁判を支える職種として裁判所事務官のほか、裁判所書記官や家庭裁判所調査官がおかれています。裁判所書記官には、法廷で行われた手続きや内容を「調書」としてまとめる権限を与えられており、裁判手続の経過を公に証明する「公証官」としての役割と、裁判が円滑に進行するように取り計らう「コートマネージャー」としての役割があります。家庭裁判所調査官は、家庭裁判所で扱われる家事事件や少年事件などについて、背景や原因などを調査し、裁判官に報告することが仕事です。裁判官は調査官の報告に基づいて最も適切な審判や家事事件においては調停を実施します。
裁判所職員における総合職と一般職の違いは?
総合職(裁判所事務官)試験は政策立案に関する能力を有するかどうかを重視して採用試験が実施されており、採用された後には裁判部と事務局の双方に携わりながら、日本の司法のあり方を制度設計を通してデザインします。一方、一般職は的確な事務処理に必要な能力を有するかどうかを重視して採用試験が実施されています。裁判所では採用時の区分にかかわらず、能力と勤務成績次第で昇進の道が開かれています。
裁判所事務官の勤務地と待遇
現在、日本には8が所の高等裁判所が配置されていますが、採用後は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所で勤務することになります。総合職は、所属の高等裁判所所在地での勤務が中心となり、総合職の多くは最高裁判所での勤務も経験します。異動は概ね3年を目安に行われ、上位ポストに昇進するにつれて、他府県への異動が行われることもあります。 裁判所事務官の給与は国家公務員試験採用者と同じになっており、期末・勤勉手当が1年間に俸給月額などの約4.5か月分のほか、住居手当や扶養手当などの各種手当が支給されています。 〈育児休業も国家公務員と同様、子が3歳に達する日までの希望する期間、休業が認められます。 そのほかにも共済組合制度が設けられており、職員とその家族の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療保険及び年金制度が用意されています。
裁判所事務官入職後のキャリアアップ
裁判所事務官に採用された後には、裁判部では裁判所書記官、主任書記官、次席書記官、主席書記官と昇進の道が開かれています。裁判所書記官になるためには、裁判所職員総合研修所入所試験に合格し、埼玉県和光市にある裁判所職員総合研修所の裁判所書記官養成課程に入所する必要があります。事務局では係長から課長補佐、課長、事務局次長、事務局長という昇進コースになります。裁判部と事務局では相互に異動、昇進が行われています。
※上記は地方裁判所を基準としたキャリアイメージになります。
裁判所事務官になるには?
人事院が行っている国家公務員の採用試験とは別に、裁判所が独自に実施している採用試験に合格し、採用されることが必要になります。筆記試験では基礎能力試験と専門試験、論文試験が課せられ、人物試験では個別面接が実施されます。総合職では人物試験に集団討論が加わります。
裁判所事務官として採用されるまでの流れ
一次試験や二次試験に合格し(総合職は三次試験)最終合格者として採用候補者名簿に名前が記載されると、勤務希望地や成績等を勘案の上、欠員のある裁判所に推薦され、それぞれの裁判所で意向照会や面接等を経て、試験の実施された翌年の4月1日付で採用されます。
1:受験資格
受験資格には学歴や学部などの要件はなく、年齢要件が基本となるので、法学部以外の学部の方も多く合格しています。具体的には裁判所事務官(一般職)の場合、令和6年度の採用試験では、平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた者が受験資格となっています。
なお、日本国籍を有しない者や国家公務員法38条の規定に該当する者など、一部試験を受けられない場合があります。
2:受験地
裁判所事務官(一般職)の場合、1次試験及び2次試験の筆記試験の試験地は、希望する勤務地にかかわりなく、全国の試験地から受験に便利な試験地を選択することができますが、この場合、2次試験の筆記試験の試験地は、1次試験の試験地と同じであることが必要です。また、2次試験の人物試験は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の試験地から選択します。裁判所事務官(総合職)の場合もおおむね同様ですが、の3次試験(人物試験)は東京都で実施されます。
令和6年度の場合
| 一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)1次受験地 |
|---|
|
3:試験・採用スケジュール
令和6年度の場合
3月15日から受験の申込受付が開始となり、1次の筆記試験が5月11日に実施されました。
総合職は6月8日に2次試験の筆記があり、総合職も一般職も6月10日から人物試験が開始されました。最終合格発表は7月31日です。その後、裁判所への推薦、意向紹介、面接等を経て、翌4月1日付で採用となります。
4:試験科目・試験内容
筆記試験は、基礎能力試験と専門試験、論文とに大きく分かれています。専門試験は総合職では択一式と記述式がともに課せられますが、一般職(大卒程度)の場合は、令和7年度の試験から、今まで課せられていた専門科目(憲法)の記述試験が廃止されるこので、併願しやすい状況になっています。面接については、総合職で2次試験と3次試験で2回、一般職では2次試験の際に1回あり、それぞれの試験が全体評価のどのくらいの割合になるかも受験案内で公表されています(筆記から面接まで得点が積み上げられていく方式)。総合職も一般職も面接の配点が高いように感じる人もいるかと思いますが、成績開示をしてみると、筆記の点数も最後まで影響していることがわかります。
裁判所事務官の試験によくあるQ&A
裁判所事務官の試験によくあるQ&Aは、最高裁判所のサイト内に記載がありますのでご参照ください。
裁判所事務官の難易度は?
国家公務員の試験と構成が類似しており、行政府と司法府という違いはありますが、科目ごとの難易度を見ても国家公務員に準ずるレベルになります。一般的な地方自治体の採用試験よりも難易度は高いといえるでしょう。
裁判所事務官と家庭裁判所調査官は併願可能?
裁判所事務官と家庭裁判所調査官は、1次の筆記試験の試験日が同一であるため、併願はできません。家庭裁判所調査官補の試験については、法律科目だけの選択で受験ができるようになったので、法学部の人などは検討の余地がありますが、仕事の内容は大きく異なりますので、どのようなことを仕事にしたいのかを考えて選択しましょう。
裁判所事務官試験の対策
一般的な公務員試験対策として、数的処理や専門科目の勉強をしっかり行うとともに、司法の場で働く意義や仕事理解を進めることが大切になります。
裁判所事務官の1次試験
基礎能力試験は令和6年度から出題数・科目が削減され、数的処理・文章理解・時事から30問が出題されるようになりました。国家公務員の採用試験では、社会科学・人文科学・自然科学の時事という形で出題がなされるため、これらの科目の基礎知識をもっていると選択肢の正誤が判断しやすくなっていますが、裁判所事務官の場合は完全な時事問題です。専門科目は必須解答の憲法と民法に加え、刑法と経済理論が選択科目となっています。令和7年度からは刑法と経済理論に加えて行政法が選択できるようになるので、併願しやすくなります。どの科目を選択するかは、試験当日に問題を見てから決めることができます。
裁判所事務官の2次試験
総合職(大卒程度)の場合は2次の筆記試験で民法と刑法の記述試験と政策論文が、一般職の場合は小論文が課せられます。一般職の小論文は、法律の専門記述とは異なり、一般的な課題に対して、文章による表現力や課題に対する理解力を見るもので、1次試験と同日に実施されますが、評定は2次試験に含まれます。また、総合職で特例を希望する(一般職も併願する)場合は小論文を受験することが必要です。面接は、総合職(大卒区分)では、2次試験と3次試験の際に個別面接があり、加えて3次試験では集団討論があります。一般職では2次試験で個別面接があります。
公務員試験対策ならLEC
適正・公正な裁判を支えるという非常に大きな意義のある職場として人気も高いですが、専門科目の難易度が高いうえ、面接ではコミュニケーション能力や対応力をよく見ているところから、模擬面接などを通して、さまざまな質問に答える練習や、予期せぬ質問にも対応できる力が必要になります。LECでは1次試験の前から面接対策ができるのに加えて、長年の面接データが蓄積されています。安心して最終合格まで到達できるフォロー制度も充実しています。勉強だけでなく、総合的な対策ができるのはLECです。
まとめ
裁判所事務官になるためには、専門試験をしっかりと勉強することが必要になります。裁判所ということで法学部でないと難しいのでは?と考える方も多いと思いますが、裁判所の採用サイトにも記載があるように、法学部でなくても一からLECで勉強して合格した人も多いです。筆記も面接も総合的な対策ができる予備校をぜひ選んでください。いっしょにがんばりましょう!
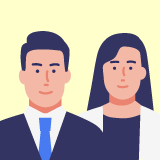
- 監修者:LEC実力派の講師陣
- LECは公務員試験の指導実績30年以上!
公務員試験を知りつくしたプロ!LEC講師陣が全国で公務員を目指す受験生のために丁寧に指導。
経験豊富な受験指導のプロが受験生の疑問や悩み・不安を解消し、最終合格・内定まで、完全サポートしていきます。
合格に導く実力の講師陣










