更新日:2024年9月27日

公務員は仕事が楽な分給料はそれほどでもないといわれることがありますが、民間の仕事や年収給与も業種により様々ですし、公務員も同様です。公務員の仕事の忙しさも国家総合職と一般職では当然異なりますし、地方公務員も市区町村などの基礎自治体といわれる職種と都道府県などの広域自治体といわれる職種では違います。忙しければ忙しいほど給料が高いとも必ずしもいえません。ここでは、これからの仕事選びに役に立つ程度で、大体公務員の年収・給与はどれくらいで、民間とどれくらい違うのか、最新の情報を元にご紹介します。
- 目次
- 公務員の平均年収はどれくらい?
- 国家公務員の平均年収は600〜800万円
- 地方公務員の平均年収は600〜700万円
- 公務員の平均給料
- 民間企業と比較すると?
- 公務員の初任給や初年度の平均年収とは
- 公務員の給料・待遇の特徴は?
- 年功序列で安定している
- ボーナスは年間で4.5か月分の月給!
- 手厚い福利厚生
- 公務員の退職金は?
- 公務員の各種手当とは?
- 公務員の給料は、職種や年齢で結構違う?
- 国家公務員と地方公務員の違い
- 職種ごとの違い
- 自治体による違い
- 【20代・30代・40代】年齢ごとの違い
- 魅力的な待遇。公務員になるには?
- まとめ
公務員の平均年収はどれくらい?
公務員の年収は国家公務員の場合は680万円程度、地方公務員の場合は約660万円程度となっています。公務員の地位は法律で定められているため、年収が大幅に低下したり、不当に解雇されることはほどんどありません。そのため、公務員は安定した職業といえるでしょう。
国家公務員の平均年収は600〜800万円
人事院 令和4年度国家公務員給与等実態調査の結果によると、国家公務員の平均年収は600から800万円程度です。しかし、全ての国家公務員がこの年収を貰えるわけではないことに注意してください。
この年収数値は、あくまでも全ての国家公務員を平均して出した年収数値であり、年齢や職種は考慮に入れられていないからです。公務員は所属しているだけで毎年給料が上がっていきますから、若いうちの給料はこれらの年収より低くなります。また国家公務員の月収は令和6年度国家公務員給与等実態調査の結果によると、国家公務員の平均給与月額は414,801円です。
公務員の給与は「俸給表」で定められており、俸給にボーナスを加えたものが公務員の給与となる計算です。「俸給」とは、職務の難しさや責任の度合いなど仕事内容に応じた給料のことです。国家公務員の場合なら、大卒の事務職は「行政職俸給表(一)」、国税庁の職員など税金関係の業務を担当する職員は「税務職俸給表」を使います。税務職俸給表の場合、月収は429,500円となり平均を超えますが、行政職俸給表(一)の場合、月収は405,378円となり、平均を下回るのです。
地方公務員の平均年収は600〜700万円
総務省 令和5年度地方公務員給与実態調査結果等の概要によると地方公務員のうち一般行政職の平均給与月額は平均年齢42.1歳で315,159円円です。そのため年収は単純計算すると、ボーナス抜きで380万円です。
ただし、ひとことに地方公務員といっても、都道府県などのいわゆる広域自治体から、市区町村などの基礎地自体まで様々です。人口50万人以上の政令指定都市は、規模が大きいため県の権限がある程度移され、行う業務も多くなります。地域内の人口が5万人以下であれば市ではなく町村と呼ばれ、その町や村役場の職員も地方公務員です。政令指定都市の職員は県庁よりも年収が高くなりますが、市役所や町村役場になると県庁よりも給料が低くなります。
公務員の平均給料
国家公務員・地方公務員の平均給与額は以下の通りです。
| 俸給(基本給) | 323,823円 |
|---|---|
| 地域手当等 | 44,134円 |
| 俸給の特別調整額 | 12,627円 |
| 扶養手当 | 8,189円 |
| 住居手当 | 7,628円 |
| その他 | 8,977円 |
| 平均給与月額 | 405,378円 |
| 都道府県 | 政令都市 | 特別区 | 市 | 町・村 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.8歳 | 40.2歳 | 42.1歳 | 41.3歳 |
| 平均給与月額 A+B |
407,064円 | 439,873円 | 420,681円 | 402,039円 | 361,255円 |
| 平均給料月額(A) | 319,151円 | 319,668円 | 297,057円 | 315,844円 | 302,172円 |
| 諸手当月額(B) | 87,913円 | 120,205円 | 123,624円 | 86,195円 | 59,083円 |
上記の他にボーナスに相当する賞与、期末手当・勤勉手当が毎年2回(6・12月)に支給されます。国家公務員の場合、賞与の額は給与の4.4カ月分が支給されるため、令和6年度国家公務員給与等実施調査の結果/国家公務員の平均給与を参考に算出すると(月額平均給与額414,801円×4.4ヵ月)=1,825,124円が支給されることになります。
地方公務員の賞与も国家公務員の賞与額に連動されます。
人事院 令和6年度国家公務員給与等実態調査の結果 総務省 令和5年4月1日地方公務員給与実態調査結果
民間企業と比較すると?
国税庁令和4年民間給与実態統計調査によると、給与所得者数の平均給与は458万円となっています。男女別にみると、平均給与は男性568万円、女性314万円となっており男女の格差が著しいという民間企業の特徴が明らかになっています。
平均年収で見れば公務員の給料は民間企業より高く、安定しているのが特徴です。ただし、あくまで平均年収なので、すべての公務員の年収が600万円を超えているわけではない点に注意しましょう。
公務員の初任給や初年度の平均年収とは
大卒程度の場合、国家公務員・地方公務員の初任給・平均年収は以下の通りです。
平均年収については12カ月分の給料に加え、ボーナスに当たる賞与を加えた額になります。賞与は国家公務員の場合、給与の4.4ヵ月と発表されており、地方公務員の場合でもほとんどの場合、同程度の賞与が支給されます。
| 初任給 | 平均年収 | |
|---|---|---|
| 国家公務員(一般職・大卒程度) | 242,640円 | 約665万円 |
| 地方公務員(都道府県) | 190,966円 | 約650万円 |
| 地方公務員(政令指定都市) | 186,699円 | 約696万円 |
※地方公務員の平均年収は、一般行政職:平均給与月額×12ヵ月+年額支給手当(期末手当・勤勉手当)で算出しています。(年額支給手当は令和3年度を参考としています。)
人事院 国家公務員の給与(令和6年版) 総務省 令和3年地方公務員給与の実態
公務員の給与は給料に加え、地域手当などの手当てが支給されるため、上記の金額より多くの額が支給されることがあります。
- 国家公務員の場合
- 地域手当 東京都特別区の場合、支払金額の20%分 大阪府、横浜市の場合、支払金額の16%分
- 本府省業務調整手当 行政(一)1級の場合、月額7,200円
一見すると、民間企業に比べて低く感じる方もいると思われます。しかし、公務員の給料は俸給表によって決まっており、確実に階段状で上がっていくため、何年後にはいくら位になると予測が立てやすくなっています。
公務員の給料・待遇の特徴は?
年功序列で安定している
民間企業の給料も正社員であれば基本年功序列ですが、仕事で挙げた業績で大きく変わってきます。就職した当初から商品企画や販売促進等で業績を出していけば同僚に大きく差をつけてどんどん昇進、昇給していきます。これが民間企業の特徴とも言えるでしょう。ただ、中高年になると頭打ちになってきてこの昇進、昇給のスピードが鈍ってくる。大体このようなカーブを描くことになります。
これに対して、公務員の給料つまり基本給は、法律に書かれている俸給表によって決まっています。初任給や最初の昇進、昇給のスピードは民間企業に及びませんが、その後は階段状に着実に上がっていきます。この俸給表を見れば大体何歳でいくらくらいもらえて生涯年収がどれくらいになるかがわかる、という意味で公務員は年功序列で安定している、といえるでしょう。
地方公務員の場合も、事情はまったく同じで、きちんと条例で職員の給料額、手当額が定めてありますし、ほぼ国家公務員の場合に準拠、連動して決定されることになっていますから、やはり民間企業に比べて安定しているといえるでしょう。
ボーナスは年間で4.4か月分の月給!

民間企業でのボーナスに相当する賞与は、期末手当、勤勉手当と呼ばれます。
そして、国家公務員の賞与の額は、人事院という国の行政機関が、人事院勧告という形で給与の方針を示し、それに基づいて法律で決まります。この人事院勧告は、民間の給与実態を踏まえて増減の調整がなされるので、景気変動の影響をある程度受けますが、その変動幅は小さいものに抑えられています。そして、賞与は給与の何か月分、という形で毎月の給与を基準に計算されます。したがって、給与が増えると賞与も連動して増えていく仕組みです。
なお、地方自治体の賞与も、概ね人事院勧告に連動しています。
手厚い福利厚生
公務員の休暇には、年次休暇として年次有給休暇、有給、年休、それから病気休暇、特別休暇、介護休暇があります。有給は1年間に20日あります。特別休暇には、結婚休暇、出産休暇、忌引、ボランティア休暇、7月から9月までの連続3日間の夏季休暇があります。
国家公務員宿舎に関しては、財務省が保有管理している各府省合同宿舎が原則ですが、これとは別に各府省独自に宿舎を保有しているところもあります。また、テニスコートやプールなど各府省独自に福利厚生施設を充実させているところもあります。職場内でのクラブ活動、レクリエーション活動も活発になされています。
民間企業の場合、医療は健康保険、年金は厚生年金保険と分かれていますが、公務員の場合は、これらをまとめた共済組合というものがあります。共済の短期給付事業が医療などで、長期給付事業が年金です。各府省に共済組合が設置され、職員はこれに加入することになっています。この各府省の共済組合の連合体として国家公務員共済組合連合会があり、その直営の病院や各種宿泊・保養施設があり、組合員が優先的に使用できる仕組みです。地方公務員の場合も同様の共済制度があります。
公務員の退職金は?
令和4年度内閣人事局発表の国家公務員退職手当実態調査によると、定年を迎えた国家公務員のうち常勤職員の退職金は、平均勤続年数35年11カ月で平均2,112万円、そのうち一般事務を行っている行政職俸給表(一)適用者に限ると、平均勤続年数38年10ヵ月で2,111万円でした。
地方公務員のうち都道府県の退職金の平均は令和3年度で全職種では全退職者の平均が約1,247万1,000円で定年退職者の平均が2,103万2,000円でした。
長引く不況の中、民間企業では退職金そのものを廃止したり、毎月の給与に上乗せして支給するなど、退職時に必ず退職金が支給されるとは言難い状況が生まれつつあるなかで、公務員の場合は、確実に退職金が支払われる制度となっており、将来に向けての安心感が違います。
公務員の各種手当とは?
民間企業の場合、残業手当や休日出勤手当などの法律で決められている手当てもありますが、住居手当や賞与などは法律で定められていないため、支給するかどうか、いくら支給するかどうかは企業が決めてよいこととなっています。ただし公務員の場合、住居手当や賞与など全ての手当ての内容・支給額は法律で決められています。
国家公務員の手当ては以下の通りです。
| 生活補助給的手当 | 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当 |
|---|---|
| 地域給的手当 | 地域手当、広域移動手当、特地勤務手当、寒冷地手当 |
| 職務の特殊性に基づく手当 | 俸給の特別調整額、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当 |
| 時間外勤務等に対して支給する手当 | 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当 |
| 賞与等に相当する手当 | 期末手当、勤勉手当 |
| その他 | 本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、研究員調整手当 |
- \まずはここからスタート!/
- 資料を請求する
公務員の給料は、職場や年齢で結構違う?
国家公務員と地方公務員の違い
公務員には国家公務員と地方公務員があります。国家公務員は霞ヶ関の中央省庁として1府12省庁で働く仕事と、全国にある各府省の地方機関の仕事です。中央省庁の仕事が国会に提出する法案の作成や予算組みなど、また、国会対応などの仕事であるのに対して、地方機関の仕事は警察庁から地方整備局など実に様々です。さらに国家専門職として、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官、防衛賞専門職員、法務省専門職員などがあります。
また、以上の内閣を頂点とする行政府の職員のほかに、立法府の職員として、衆議院・参議院の事務職員、各法制局、国立国会図書館職員、裁判所の職員として裁判所事務官、家庭裁判所調査官の仕事などがあります。
地方公務員にも都道府県などの広域自治体と市区町村などの基礎自治体があり、基礎自治体が窓口業務など住民密着型の仕事なのに対して、広域自治体は国や他都道府県、企業、団体などが相手の仕事です。
職種ごとの違い
公務員の給与は職種によって異なります。
国家公務員の場合、前にも述べたように行政職俸給表(一)は大卒の事務職職員が、税務職俸給表は国税庁の職員など税金関係の業務を担当する職員が適用されます。
専門行政職俸給表は特許庁の審査官や航空管制官など専門的な知識が必要とされる職員が適用されます。
| 平均給与月額 | |
|---|---|
| 行政職俸給表(一) | 405,378円 |
| 税務職俸給表 | 429,500円 |
| 専門行政職俸給表 | 450,499円 |
地方公務員については自治体ごとに異なります。各自治体の給与は財政状況に大きく影響されるため自治体によって様々です。
| 平均給与月額 | |
|---|---|
| 一般行政職 | 319,151円 |
| 警察職 | 328,653円 |
| 消防職 | 315,492円 |
| 高等学校教育職 | 369,044円 |
| 小・中学校教育職 | 353,669円 |
人事院 令和6年度国家公務員給与等実態調査の結果 総務省 令和5年地方公務員給与の実態
自治体による違い
令和4年度における平均給料のランキングは以下の通りです。
| 順位 | 自治体名 | 平均年齢 | 平均給与月額 ※1 | 諸手当月額 ※2 | 平均給与月額 ※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川崎市(神奈川県) | 41.6歳 | 322,300円 | 141,338円 | 463,638円 |
| 2位 | 三鷹市(東京都) | 42.0歳 | 327,300円 | 133,782円 | 461,082円 |
| 3位 | 豊田市(愛知県) | 42.3歳 | 324,700円 | 135,424円 | 460,124円 |
| 4位 | さいたま市(埼玉県) | 40.6歳 | 318,300円 | 140,207円 | 458,507円 |
| 5位 | 千葉市(千葉県) | 41.2歳 | 315,400円 | 142,060円 | 457,460円 |
| 6位 | 神戸市(兵庫県) | 42.8歳 | 327,600円 | 129,640円 | 457,240円 |
| 7位 | 厚木市(神奈川県) | 41.8歳 | 322,800円 | 133,981円 | 456,781円 |
| 8位 | 東京都 | 42.3歳 | 316,400円 | 137,195円 | 453,595円 |
| 9位 | 相馬市(福島県) | 41.6歳 | 323,700円 | 127,923円 | 451,623円 |
| 10位 | 三田市(兵庫県) | 45.1歳 | 329,700円 | 121,790円 | 451,490円 |
- ※1 平均給料月額とは、給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたもの
- ※2 諸手当月額とは、月ごとに支払われることとされている扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものである(期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含まない。)。
- ※3 平均給与月額とは、平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したもの
ランキングを見て分かるように広域自治体(都道府県庁)から基礎自治体(市役所)まで様々な自治体が上位にランクインしており、地方公務員の給料は自治体の規模に関わらず決まっていることが分かります。
また、公務員は基本給の他に地域手当などの手当てが支給されます。そのため、都市圏にある自治体が上位にランクインされやすくなっており、その一方で都心から離れている地方都市や過疎地域と呼ばれている自治体は比較的、給料が低くなってしまいます。
【20代・30代・40代】年齢ごとの違い
公務員の給料は、年功序列といって、年齢や勤続年数に比例して増えるのが特徴です。最近は、職員の士気向上の観点から、完全な年功序列ではなくて、部分的に業績連動制を導入する官公庁も増えてきましたが、基本的には年功上列で決まってきます。
どこの官公庁かということによっても異なりますが、おおよそ以下のようになります。
20代は約300万円から450万円超、最初のうちは民間企業に比べ低いといえるでしょう。
30代は約500万円から600万円超、中堅どころですでに平均年収に近づいてきます。結婚や出産などのライフイベントもあり、出費も増える世代です。
40代は約650万円から800万円超、公務員でもこれくらいの世代になると個人差が生じます。部課長など責任ある地位につくため収入もそれにふさわしいものになります。
50代は約800万円から900万円超、20代の時と比べると倍近くになる例も少なくありません。役職も部局長など組織のトップ、またはそれに順ずる地位が多くなるため、それにふさわしい収入となります。
魅力的な待遇。公務員になるには?
公務員試験はその職種により様々ですが、ざっくり説明すると国家公務員でも地方公務員でも一次試験と二次試験があり、大体一次試験が筆記試験で、二次試験が「人物試験」といわれる面接試験です。面接試験は民間企業の採用試験と大体同じですが、民間ほど積極的なアピールは必要なく、聞かれたことに正確に答えれば合格できます。
また、民間企業の就職のように中々エントリーシートを通過することができず、面接してもらえないということはなく、筆記試験に合格すれば、全員平等に面接試験を受けることができます。そうすると、一次の筆記試験が大切になってくるわけですが、これには大学入試のセンター試験同様の5肢択一試験と文章を書かせる記述試験があり、なんといっても択一試験が大切です。択一試験の科目は教養ないし基礎能力と専門があり、行政事務でも理系でも心理福祉でも教養は共通で、専門で分かれます。ただし、専門試験が課されない職種もあり、勉強量が少なくなりますから、民間企業との併願が容易となります。
公務員試験は情報が大切になってきますので、一度公務員予備校などの専門知識豊富なスタッフに相談されるのが効果的です。
まとめ
以上のように、給料は低いが仕事は楽であるとか、公務員の中でも試験の難易度が高い職種や有名な公務員ほど給料が高いとは必ずしもいえないことがお分かりいただけたと思います。高校や大学を卒業してすぐに就職したとして、人と職業の付き合いは40年余りになり、仕事イコール人生と言っても言いすぎではありません。自分の一生に大きく影響する選択ですから、できるだけ多くの情報を集めて、慎重に考え選んでいきたいところです。以上の情報が皆さんの最良の選択に役立つことができれば幸いです。
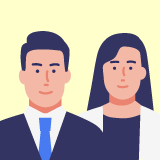
- 監修者:LEC実力派の講師陣
- LECは公務員試験の指導実績30年以上!
公務員試験を知りつくしたプロ!LEC講師陣が全国で公務員を目指す受験生のために丁寧に指導。
経験豊富な受験指導のプロが受験生の疑問や悩み・不安を解消し、最終合格・内定まで、完全サポートしていきます。
合格に導く実力の講師陣










