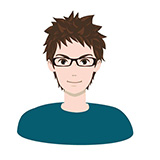
必要なものは全てここにある!
| 年齢 | 31歳 |
|---|---|
| 受験回数 | 2回 |
| 職業 | 会社員 |
| 出身校 | 明治大学大学院 |
| 受講講座 | 論文合格答案完成コース(講座) |
| 選択科目 | 免除あり:大学院卒 |
弁理士を目指した理由・きっかけ
メーカーの開発部門で開発業務に従事していましたが、今後のキャリアの可能性を広げたいと考えた時に、開発経験を活かすことができる知財業界に興味を持ちました。
知財業務について調べるなかで弁理士という資格を知り、自分が知財業界に向いているのか試すために弁理士試験の勉強を始めました。
LECを選んだ理由
1年目は他社の教材を用いて短答試験を合格したものの、短答対策のみであったため論文式試験が不合格でした。
論文の書き方を一から学び、多くの添削を受けたいという思いがあったため、合格実績が高いLECを選びました。
LECで受講した学習経験者向けコース・講座とその担当講師について
オンライン受講が可能なので、通勤中に視聴したり等、すきま時間を使って講義の復習をしたことで学習の定着率が上がったと思います。教材の演習問題は過去問を単元ごと(中間処理、審判等)にまとめてあるため、苦手分野を集中的に復習する等、効率的に学習を進めることが出来ました。
また、演習問題以外のインプットテキストや判例集等の教材が豊富なので、本講座のテキスト以外の余計な教材に手を出す必要がなく、これらを完璧にすれば大丈夫だと思いながら勉強することが出来ました。本講座は論文集中答練、実戦答練、完成答練がついており、たくさんの演習機会を確保することが出来、添削内容を復習することで自分の答案を磨くことが出来たと思います。年明けから毎週、答案を提出する必要があるのでペースメーカーとしても非常に有効でした。
また、他の受講生の優秀答案を見ることが出来るので、自分が不足している箇所を知ることが出来ることも有益でした。
納冨先生の講座では、システマチックに論文を書くことを教えていただきました。記載すべき項目を落とさない、きちんと「あてはめ」を行う等の、必要な技術を学ぶことで論文問題に対する解像度が上がりました。
また、先生は経験豊富な指導実績があるので、受験生が弱点としやすい箇所や大事なポイントを特に強調して話してくれるので、本講座を受講して良かったと感じています。先生がおっしゃる「大樹に寄れ=皆が書くことは自分も書く)」という考えは論文試験で非常に大切な考えで、答練や模試の際も意識しました。
LECで受講した答練・摸試について
- [受講答練・模試]論文公開模試 論文実戦答練 論文直前答練 論文プレ模試(論文完成答練) 論文集中答練
-
答練や模試では重要度の高い論点が出るので、答練を軸に学習を進めれば自ずと力がつくと思います。たまに本試で問われることが少ない論点が出る場合もありますが、本番でも同様のことが起こりうるので、そのような状況でも答案を作成する力も身に付きました。
また、他の受験者との相対的な立ち位置が分かるので、点数が良くない時は勉強のモチベーションが上がりました。
LECで受講したスポット講座について
- [受講講座]各種道場・その他:納冨美和の論文最終ヤマ当て道場
- 本試直前に行われる講座ですが、これを受講したことは大正解でした。納冨先生が試験委員のメンバーを見て出題される可能性の高い分野の問題演習を行う講座ですが、今年は特許で的中していたため、本試で慌てずに問題を解くことが出来ました。毎年的中するかどうかは分かりませんが、本講座で出題される問題を直前期に正解出来れば自信をもって本試に臨めるという効果もあると思います。
LECの教材や学習システムについて
講義映像をダウンロードできるため、通勤中に視聴する等、すきま時間を使って学習することができるのは大変助かりました。答練の答案提出や答案返却が全てオンラインで完結することも非常に便利です。添削についても、いろんな採点官に採点していただけるので、どの採点者に当たっても一定の点数を取ることをモチベーションに答練に臨むことが出来ました。
短答式試験対策でやって良かったこと
1年目はLECではなく他社の講座で勉強進めていましたが、短答対策でやってよかったことは条文の理解です。過去問をひたすら解くだけでは文章やシチュエーションを変えられたときに対応できないため、まずは条文を理解することが大切だと思いました。
また、過去問を解いて答え合わせをする際、設問ごとではなく、枝ごとに正解できたのかを確認することが大切だったと思います。枝単位ですべての過去問を解けるようになった時、合格する力が身についていたよう思います。時間配分を体感するために、模試を受けたことも非常に役立ちました。
論文式試験対策でやって良かったこと
実際に答案を書くことが非常に有益でした。手が疲れたり、時間が足りなかったり、分かっていても文章に出来なかったり等の経験は実際に手を動かさないと分からないことです。書くことを繰り返すことで、時間配分や講義で学んだ「あてはめ」等を改善することが出来たと思います。過去問演習や答練の復習は答案構成で終わらせることが多いと思いますが、上記を経験することで時間配分や答案構成の内容などを厳しく行うようにしたことも良かったと思います。
また、答練や模試を徹底的に復習することが良かったと思います。何週も繰り返すことで重要な論点をマスターし、頻出論点についてはテンプレート化することで時間不足も解消されました。答練や模試は自宅受験でしたが、可能なら現場受験することをお勧めします。本試の特許では手が震えてしまったので、受験生が集まる現場受験をしたほうが本番に近い空気感も体感できると思います。
口述試験対策でやって良かったこと
論文合格の自信がなかったため、口述試験対策は論文合格発表後から取り組みましたが、これはお勧めしません。9月くらいには始めておけば、もう少し余裕をもって学習を進めることが出来たと思います。
短期間で合格できた要因としては2つあると思います。まずは過去問を完璧にすることです。基本的には過去問に似たような問題が出やすいため、それらを徹底する中で、関連条文を読み込むが重要だと思います。
また、口述模試を複数回受けることです。テキストを見ながら暗唱できても、実際に対面で聞かれるとうまく答えられないことがあるため、早い段階で口述模試を受けて体感することが大切です。
学習時間を捻出するために工夫したこと
通勤中の時間を使用する等、すきま時間を使って学習することが大切だと思います。特に判例や趣旨などの暗記系は、このような時間を使って少しずつ暗記して、机上で勉強出来るときは問題演習に充てることが効果的だと思います。
また、試験が近付いたら趣味の時間を我慢する等して時間を作り出すことはしましたが、睡眠時間だけは十分に確保していました。
通学、または通信での受講を選択して良かった点や反省点
私は通信を選択しましたが、通信を選んで正解でした。充分な環境が整っているので通信のデメリットを特に感じることなく、学習を進めることが出来ました。納冨先生の講座を受講していましたが、先生も「通信の受講生の方が多く、合格者も多数いる」とおっしゃっていたので、不安なく学ぶことが出来ました。通学だと目の前に受験生がいるというモチベーションが大きいと思われます。
今、合格して思うこと
嬉しさと安堵感の両方があります。また、難関資格と呼ばれる弁理士試験に合格したことは自分の自信になりました。受験期間を振り返ると、勉強自体は楽しいと思うことがありつつも、合格しないと報われないというストレスがありました。企業の知財部で働いているため、弁理士試験で学んだことや今後弁理士として学ぶことを会社に活かせるような弁理士になりたいと思っています。
弁理士試験の勉強はつらい時もあると思いますが、その分、合格したときは嬉しさが大きいです。LECで学習することが合格への近道だと思うので、皆様も頑張ってください。







