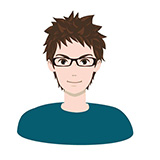
楽しい受験生活でした!
| 年齢 | 32歳 |
|---|---|
| 受験回数 | 2回 |
| 職業 | 会社員 |
| 出身校 | 京都大学大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 |
| 受講講座 | 1年合格ベーシックコース インプット+アウトプット一括 論文シーケンスコース |
| 選択科目 | 免除あり:理工Ⅲ(化学) |
弁理士を目指した理由・きっかけ
「理系 資格」
新卒で希望と異なる部署に配属され、漠然と今後のキャリアに不安を覚えた頃に、何か技術に関わる資格の勉強をしようとネットで調べたことが弁理士という職業を知ったきっかけです。ただ、弁理士資格は最難関資格と呼ばれる資格の一つであり、かつ独学での合格が非常に難しいということで、知財実務を何も知らない当時の自分がお金と時間を投資して挑戦するのはリスキーだと考え、まずは知的財産管理技能検定からチャレンジすることにしました。
その後、知的財産管理技能検定2級まで合格し、縁あって知財部門へ異動し知財実務に関わり始めたことを受けて、弁理士を本格的に目指すことにしました。
LECを選んだ理由
合格実績が一番であったことが理由です。LECと比べて価格が安い他の予備校との間で非常に悩みましたが、ここでケチってダラダラと長期間受験に費やすよりも、合格実績が一番のLECにお世話になってさっさと合格した方が良いと考えました。一発合格はできませんでしたが、安くはない金額を投資したことでモチベーションの維持に繋がった面もありました。
LECで受講した初学者向けコースとその担当講師について
宮口先生の1年合格ベーシックコースの通信講座を受講しました。宮口先生のコースを選んだ理由は、合格実績(一発合格)が高かったためです。
ベーシックコースの良い点は、初学者を対象とする体系的な講義カリキュラムはもちろんのこと、答練や模試等のアウトプット講座も充実している点です。答練や模試は単体で受講すると結構なお金がかかりますが(2年目に受講した時にびっくりしました)、ベーシックコースには十分なアウトプット講座がセットでついているため、これをこなすだけでも相当力がつきました。また、短答試験向けのテキスト「短答アドヴァンステキスト」はLECテキストの中でも至高のテキストだと思います。
宮口先生の講義についてですが、最初に受講したときの感想は、「めちゃめちゃ分かりやすい!声が良い!!やっぱプロはすげえ!!!」でした。世の中には退屈なセミナーや研修も多くありますが、宮口先生の講義はそれとは無縁で、楽しく法律について学ぶことができました。また、高校時代に古典単語をゴロだけで覚えていた私にとって、宮口先生のゴロテクは非常に頭に入りやすく、伝授いただいたゴロテクは短答試験、論文試験、口述試験全てにおいてもとても役立ちました。
私は完全通信でしたので、主に夜や早朝に講義を聞いていましたが、ハイテンションな宮口先生のおかげでほとんど眠くならなかったのも良かったポイントです。PCのスピーカーから流れる宮口先生の「うええええええい!!」で家族がよく笑っていましたね。
LECで受講した学習経験者向けコース・講座とその担当講師について
1年目の受験で論文試験不合格となったため、宮口先生の論文シーケンスコースを通信で受講しました。1年目のベーシックコースを本当に楽しく受講できたので、他の先生との比較は全く行わず受講を決めました。
論文シーケンスコースは論文試験に特化したコースで、インプット・アウトプットともに充実しています。特に最初のインプット講座である「一行問題対策編」のテキストは、短答試験対策で疎かになりがちな趣旨がまとめられており、まさに欲していたテキストだったため、通勤時間や隙間時間など暇さえあればこのテキストを読んでいました。口述試験当日の控室で、受験生活最後に読んだテキストもこの一行問題対策編テキストでした。
論文試験は相対評価であり、論文の書き方の流儀も先生によって若干異なりますし、答練や模試での採点も採点者によってブレがあります。そのため、受験生は色々な情報に惑わされてしまいがちですが、宮口先生は「これは書かなくていい!こういう答案が(でも)受かるんだ!」とはっきりと言ってくださるので、宮口先生の教えを第一に信じ続けたことで一本筋の通った答案が書けるようになったと感じています。
LECで受講した答練・摸試について
- [受講答練・模試]論文公開模試 論文実戦答練 論文直前答練 論文 プレ模試(論文完成答練) 論文集中答練 論文合格答練 短答公開模試 短答実戦答練
- 1年合格ベーシックコースや論文シーケンスコースについている答練の他、論文直前期の答練・模試パックを受講しました。特に論文試験は、どんな問題が出ても合格点の付く解答ができる(ホームランを狙うのではなく打率を極限まで上げる)ことが重要と思いますが、LECの答練や模試の問題は非常にバラエティに富んだ問題が多く、本試験よりも難しいと感じる問題も多数ありました。そのような問題に冷や汗をかきながら食らいついたことで、新作問題へ対応する力を鍛えられ、最後にはどんな問題が来ても合格点を勝ち取る自信をつけることができました。
LECで受講したスポット講座について
- [受講講座]
宮口聡の理想と現実答案
宮口聡の論文ヤマゴロ講座
宮口聡の短答ゴロテクコンプリート -
宮口先生の「短答ゴロテクコンプリート」「論文ヤマゴロ講座」「理想と現実答案」を受講しました。特に印象的だったのは、「短答ゴロテクコンプリート」で宮口先生が問題文を一切読まずにテクだけで解答枝を答えていたことです。当時、講義を聞きながら思わず笑ってしまいました。
「論文ヤマゴロ講座」も1年目のコースと並行して受講したので、知識の浅い当時の私は、なかなか消化しきれませんでしたが、論文の基本型をしっかりと身につけることができたこと、見解論述対策など他の講座ではなかなか得られない知識を得られたことはとても良かったと思います。
「理想と現実答案」は言わずとしれた過去問講座ですが、宮口先生の答案をお手本として過去問を回すのにとにかく使い続けました。「理想と現実答案」以外で過去問を一切見ていないので、他の過去問答案との比較はできませんが、宮口先生の答案は本試験の会場で現実的に書くことができるかを意識して練り上げられた答案だと思いますので、受験生にとっては間違いなくお手本になる答案だと思います。
LECの教材や学習システムについて
LECの教材はその実績に裏打ちされた非常に質の高いものだと思います。特に基幹講座のテキストや答練・模試はその内容が練り上げられており、LECの教材を信じて最後まで取り組むことができました。
学習システムについても、好きな時間に講義を受けられる通信Webシステムは良かったと思います。私はあまり他の機能は活用しませんでしたが、質問制度や音声ダウンロード機能など、受験生に必要な機能は充実していると思います。
短答式試験対策でやって良かったこと
短答試験対策では、法文集に情報を一元化したことが非常に良かったと感じています。条文の文言だけでは読み取れない知識(判例、審査基準、逐条解説ベースの知識等)や、過去問・答練において間違えた枝のポイントを全て法文集に書き込みました。短答試験前日と当日の午前中に法文集の書き込みを全て見直したことで、効率よく最後の仕上げをすることができました。
また、宮口先生の教えに従い、10年分の過去問の全枝をA~Dランクに振り分け、自信をもって答えられないCランク枝、答えを間違えてしまうDランク枝をとにかく無くす作業を繰り返しました。また、答えは分かるけれど根拠条文が分からないBランク枝も可能な限り減らすよう、答練や模試を解く際にもできるだけ根拠条文も答えるように意識していたことは、その後の論文試験、口述試験でも活きたと感じています。
論文式試験対策でやって良かったこと
趣旨問題対策です。私は、論文シーケンス講座の一行対策編レジュメ(趣旨がまとまっているもの)をボロボロになるまで繰り返し読み続けました。近年の本試験における趣旨問題のウェイトはそれほど大きくないですし、上手く解答できなくても差はつかない、というご意見もよく耳にします。しかし、論文試験に落ちた1年目の私の経験からすると、趣旨問題が分からないときのメンタルへのダメージは配点以上のものです。特に趣旨問題は最初の方で問われることが多いため、その後の問題を冷静に解くメンタルを維持するための精神安定剤という意味でも趣旨問題対策をしっかりとやっておくことは重要だと思います。私の場合、最後には「自分が書けない趣旨はほとんどの受験生が書けない」と自信を持って思えるくらいになり、試験全体を通じてメンタル面での心配がなくなりました。
また、論文試験に落ちた1年目にはできておらず、2年目にやったこととしては、答練の復習です。もちろん1年目にも答練後に解答や添削答案を見ての復習はしていましたが、ふむふむと眺める程度のものでした。2年目には、答練を解いた後にまず自己採点をし、なぜ点数を落としたかしっかりと確認し、どう書けば良かったのか自分自身で添削をするようにしました。また、添削答案が返ってきた後には、自己採点の結果と見比べて「採点に差がある箇所」を重点的に確認するようにしました。これは、自分が書けていると思っていても、実は上手く書けていない可能性のある箇所なので、自身の答案を客観視する上でも非常に良かったと感じています。このような復習を全答練・模試で行ったことで、論文試験合格レベルに到達することができたと思っています。
口述試験対策でやって良かったこと
論文試験の合格前から受験生仲間と口述練習を始めたことです。口述試験は、短答試験や論文試験とアウトプットの仕方が異なるため、早めに自分自身の癖や感覚(緊張する、頭ではわかっていても上手く口が回らない、冗長に答えてしまいがち等)を掴むことが重要です。
これは人によると思いますが、私の場合は頭の中で答えられることは、口でもほぼ同じように答えられる、という感覚を早めに掴むことができたので、アウトプットは受験生仲間との週1回程度の練習会や模試数回だけとし、それ以外の時間を使って過去問ではあまり出ていない条文や趣旨のインプットなどもしっかりと行うようにしました。
結果的に今年の口述試験はあまり過去問では出ていないところから出題されましたが、本試験でも焦ることなく解答することができました。
学習時間を捻出するために工夫したこと
私の場合は幼い子の育児もあり、かつ共働きでもあるため、弁理士試験受験を決めるにあたって子育てや家事に迷惑はかけない、と家族と約束をしました。そのため、子どもが起きている時間や家族と過ごす時間に勉強することは半ば最初から諦めていたので、それ以外の時間で学習時間を捻出しました。
具体的には、通勤時間と子どもが寝た後・起きる前の時間で学習時間を捻出しました。受験生を始めた頃は夜型だったのですが、子どもの寝かしつけで一緒に寝落ちしてしまうことも多く、また、夜は疲れが溜まっていて集中しづらかったことから、途中から夜は子どもと一緒に寝ることとし、早朝に勉強するスタイルに変えました。早朝の方が集中しやすく、自分自身にも合っていたように思います。何より、夕食時に気兼ねなくビールを飲めるようになったことが一番大きかったですね。
学習時間の目安としては平日・休日関係なく1日3~4時間を目指しました。休日は通勤時間がない分、時間の確保がむしろ難しかったですが、子どもたちがのんびり寝ていてくれることを祈りながら早朝に机に向かっていました。
通学、または通信での受講を選択して良かった点や反省点
私は完全に通信でしたが、元々通学の選択肢は全くなかったので、特に通信で後悔したことはありません。通信は、自身の生活スタイルや家庭事情に合わせて受講することができ、非常に良かったと思います。もちろん、途中だらけてしまうことや講義に集中できない時もありましたが、通学の講義と同じような頻度で配信される通信講義は良いペースメーカーになりました。また、答練や模試も全て通信で受験しましたが、通学で受ければ良かったな、と思うことは特にありませんでした(論文本試験はもちろん非常に緊張しましたが、通信で大勢の試験会場に慣れていないから、ということではなかったと思います)。
今、合格して思うこと
ぼんやりとした理由から始めた弁理士試験でしたが、終わってみれば受験生生活を通して特に苦しいことやモチベーションが大きく下がることもなく、総じて楽しんで受験生活を続けられたと思います。
弁理士試験合格が、今後の自身のキャリアにどう影響を与えるかはまだ分かりませんが、一つの大きなポイントになるのは間違いないと思うので、上手く自身のキャリアに活かしていきたいと思います。
これから弁理士を目指す方、弁理士試験は決して簡単な試験ではありませんが、その分挑戦しがいのある面白い試験だと思います。ぜひ受験生活を楽しんでください!







