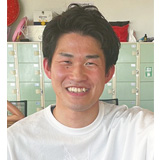
常にモチベーションとの戦い
三上 拳斗さん
| 年齢 | 29歳 |
|---|---|
| 受験回数 | 3回 |
| 職業 | 会社員 |
| 出身校 | 東東京農工大学大学院 工学府 産業技術専攻 |
| 受講講座 | 1年合格ベーシックコース インプット+アウトプット一括 Lゼミ |
| 選択科目 | 免除あり:理工Ⅲ(化学) |
弁理士を目指した理由・きっかけ
高校の進路選択を考える中で、将来の職業で研究者ではない道に興味がありました。職業を調べる中で、弁理士という職業が世の中にあることを知りました。
私自身小さい頃から新発売の商品や期間限定商品に弱いタイプでしたので、新しいものに他の人間よりも早く触れられる機会が多い弁理士という職業に興味を持ったのが最初のきっかけです。
LECを選んだ理由
新卒で入社した会社の上司や先輩で弁理士の方はみなさんLECに通われていましたので、数ある予備校の中からLECを選んだというよりも他の予備校をそれほど知りませんでした。ただ合格者が多い試験でないにも関わらず、これほどLEC出身の方が多いということはLECを選ぶことが自分にとっても最短の道なのではないかという考えでした。
LECで受講した初学者向けコースとその担当講師について
初学者向けのコースは宮口先生の1年合格ベーシックコースを取りました。
最初の方は最重要事項と思われる部分についてまとめて講義を受けられるので、勉強を進めていく上でどのあたりが勉強の柱となるのか目星をつけやすいです。おそらく私が独学でやっていると条文を頭から見始めて30条に辿り着く頃には思考停止してしまうと思います。その点からも重要な点を重要な点として教わることができる初学者向けのコースはおすすめです。テキストも法改正の影響を受けないような学習をする中で常識的な部分が集約されているので、論文試験や口述試験でも使える知識の宝庫だと思います。基本的なことでわからなくなった時はインターネットで検索する前にまず入門テキストで確認するようにしていました。
宮口先生の講義はとにかく印象に残ります。講義中によく出てくるゴロはリズムも相まって覚えやすいです。平日の仕事終わりにLECに行くと講義前に眠い時もありましたが、宮口先生の講義が始まると目が覚めます。7色の蛍光ペンを使うのも自分的に楽しかったです。
宮口先生の入門テキスト用の宮レジは入門テキストには記載されていない、青本や審査基準の重要な部分まで網羅されており、論文試験や口述試験の勉強でも活用できました。青本や審査基準を読み始めると時間がいくらあっても足りないので、宮レジは効率的に勉強を進める上でも重宝しました。
LECで受講した学習経験者向けコース・講座とその担当講師について
2年目はLゼミSpecial、3年目はLゼミを取っていました。
2年間、多くの問題に触れることができて、モチベーションの維持に役立ちました。経験のない問題に回答することは初めは動揺しますが、現場思考型の問題に慣れることができました。また、Lゼミの前半と後半の間に先生独自の講義があり、趣旨の対策や先生が作った完全オリジナル問題に取り組むことができたことも良かったです。
現場で答案を書けることも自身のモチベーションの維持につながりました。私は自宅で回答できてしまうと時間制限というストレスが弱くなってしまい、本番同様の気持ちで問題に取り組めないからです。
プライベートでは、途中で引っ越しがありましたが、土曜講義だったので、必ず通うことができたことも選んだ一因です。
LゼミSpecialではとにかく型を覚えるように努めました。安西先生は細かく指導してくださるので自分でも気付いていないミスに気が付くことができました。
馬場先生のLゼミは毎週、前の週にやった得点のトップ10が発表されます。それがとてもモチベーションの維持につながりました。私は一度もトップ10に入ったことはありませんでしたが、必ずトップになってやろうと頑張るきっかけをもらえました。また、馬場先生のLゼミでは受験生が何を書くかにフォーカスしており、他の受験生の答案を見る機会がかなりありました。自分が答案を作成する上で悩んでいることは意外と悩むに値しないことなんだと気付く機会があり、ゼミを受ける前に比べ、肩の力を抜いて論文が書けるようになった気がしています。
LECで受講した答練・摸試について
- [受講答練・模試]論文公開模試 論文直前答練 短答公開模試
-
短答の答練や模試は回数が多く、自分の弱点を知る最適な場だと感じました。また、本試験より難易度が高い気がするので、ここで合格点が取れていれば自信を持って本試験に臨むことができました。
論文の答練や模試は、採点が素早く、点数の良し悪しに関わらず講評でモチベーションを保つことができました。また、LECは他の予備校に比べて受験者が多いので、自分の現在地を把握しやすく、順位を知った上で、勉強に取り組めるのもモチベーションの維持につながりました。
口述模試は商標が苦手な受験生だったので、回答はままなりませんでしたが、講師の先生達に応援していただけたことでなんとかモチベーションを保つことができました。
LECで受講したスポット講座について
- [受講講座]
宮口聡の理想と現実答案
宮口聡の短答REVOLUTION
宮口聡の論文ヤマゴロ講座
宮口聡の短答サルベージゼミ
宮口聡の論文サルベージゼミ - 宮口先生の知財判例120%チャージは受験生の期間ずっとお世話になりました。判例は短答、論文、口述のどの試験でも問われる可能性があるので、判例集を入手できることは試験勉強を優位に進められると思います。また、ポイントとなる部分をゴロで覚えられることも良かったと思います。
LECの教材や学習システムについて
入門テキストは論文試験や口述試験でも使えました。勉強進めているとどうしても細かい点やできなかったところが気になってしまい、重要な部分を疎かにしてしまいがちでした。そんな時に入門テキストを改めて確認すると、趣旨や経緯が端的にまとまっているので重宝していました。
短答式試験対策でやって良かったこと
短答試験はとにかく過去問に当たることだと思います。私は宮口先生の短答Revolutionを取っていたので、主にその講座を利用して勉強を進めました。できる問題とできない問題を評価しておき、できない問題ができるようになるまで何周も行いました。条約の細かい点を覚えることはなかなかできませんでしたが、過去に試験で問われた点は必ず解けるようにしました。できない問題が少なくなることはモチベーションの維持のためにも大切だと感じています。
過去問で問われた部分やゴロが使える部分については四法対照にメモを残しておき、記憶の定着に努めました。勉強をする時に、条文を読んでいると眠くなってしまうタイプなので、なかなか条文を読むだけという勉強はしませんでしたが、自分がメモを書くこと、そしてそれを見ることで関連付けて記憶することができました。
論文式試験対策でやって良かったこと
初めて論文試験を受けた時、書き始めると書きたいことがどんどん出てきてしまい、書くべき部分と時間があれば記載する部分の境界が曖昧になり、重要な部分が記載が疎かになっているような気がしました。短答試験の後であったこともあり、論文を書いていると原則を書いているときに例外ばかりが気になってしまっていたのだと思います。
2年目からは過去問を中心に勉強するようになりました。過去問の勉強を進めると、問われていることは毎年全く異なるものではなく、問題自体が聞き方を変えて繰り返されているものだと知りました。ただ、過去問だけをしていると本試験で新しい問題と出会った時に動揺してしまい、答案のバランスや時間配分をミスしてしまうことも知れました。
3年目は、過去問は2年目である程度やっていたので、記憶を維持しつつ、新作の問題に手を出すようにしました。自分の性格上、わからない問題があると動揺してしまうため、その可能性を少しでも減らすためです。また、趣旨は過去問や模試で問われた点はある程度書けるようにはしていましたが、それ以外は出たとこ勝負で書くくらい勉強していませんでした。
口述試験対策でやって良かったこと
どれだけ口に出して練習できるかがポイントだと思います。ゼミのメンバーがほぼ毎日練習に付き合ってくれた点は勉強する上で良かったと感じています。心の中で答えるのと声に出して質問に答えるのでは心理的な負担が全く異なります。答えている間にちょっと気になることがあったりすると、自信のない回答になってしまい、色々なところで指摘を受けます。本番を意識できるような緊張感がある中での練習をする上では模試は重要な機会でした。
学習時間を捻出するために工夫したこと
学習時間の捻出に苦労するタイプではありませんでしたが、毎日勉強することだけはルールにしていました。そうすることで前日勉強をしてなかった分を取り返そうとする罪悪感がなく、気負わずに勉強を継続できるからです。直前期になると、丸々一日勉強しようという気持ちになるのですが、集中力はそれほど続かず、先に疲れてしまうので、毎日少しずつが良いと思っています。
通学、または通信での受講を選択して良かった点や反省点
通学で受講を選択していました。通学で良かったと思っています。Lゼミで他のゼミ生の論文答案を見ることがよくあったのですが、それがとても参考になりました。そこで記載のどこに力を入れるべきかわかってきた気がします。対面でないとわからないことだと思うので、この点はとてもメリットだと感じています。
今、合格して思うこと
とりあえず試験勉強が終わってホッとしています。思い出してみると、初めてLECに行ってみてから、ほぼ4年経つのかと思います。よく諦めずに試験を受け続けたと思います。特に3年目はモチベーションの低下を感じ、勉強に身が入らないことも多々ありました。
私が当時勉強1年目の自分にアドバイスするなら、SNSは見るなと言いたいです。どうしても他人の模試の結果が気になってしまい、一生懸命検索しては落ち込んでしまうからです。「模試で合否が決まるわけではないので、そんなに一喜一憂するな、ということと、試験が終わってからSNSはやりなさい。」という2点はあの頃の自分に言いたいです。







